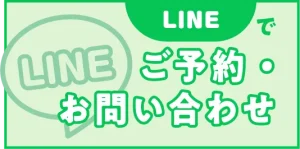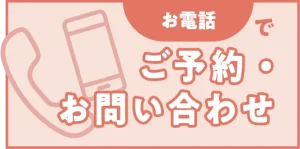鍼灸の専門家が教える!めまいが起きたときにまず試したい7つの対処法
Contents
めまいとは?タイプ別に原因を正しく知ろう
「めまい」と一言で言っても、その感じ方や原因はさまざまです。
代表的なのは、周囲がグルグル回るように感じる「回転性めまい」と、フワフワ・フラフラする「浮動性めまい」です。
中には、立ちくらみと混同されるケースもあります。
原因には、耳の内耳の異常(耳石のズレや前庭神経炎など)、脳の血流不足、自律神経の乱れ、さらにはストレス・睡眠不足・栄養不良といった生活習慣も関わっています。
めまいを効果的に対処するには、まず自分の「めまいのタイプ」と「引き金になりそうな生活習慣」を把握することが重要です。
めまいが起きたときにすぐできる7つの対処法
突然のめまいに襲われると、不安になりますよね。そんなときは、慌てずに以下の7つの対処法を試してみてください。
-
すぐに横になり、安静にする
まずは安全な場所で横になり、目を閉じて休みましょう。頭を少し高くして静かにしていることで、症状が和らぐことがあります。 -
明るさと音を調整する
強い光や騒音は症状を悪化させる可能性があります。部屋を暗くして静かな環境を保つことがポイントです。 -
水分を補給する
脱水もめまいの原因になるため、少量ずつ常温の水を飲んでみましょう。特に汗をかいた後や起床時には効果的です。 -
深呼吸して自律神経を整える
ストレスや不安による自律神経の乱れもめまいの一因です。鼻からゆっくり吸って、口から細く長く吐き出す深呼吸を繰り返してください。 -
目を閉じて一点をイメージする
目を開けると視界が揺れて不安が増すことがあります。目を閉じて、落ち着くイメージ(空や自然)を思い浮かべるのもおすすめです。 -
急な動作を避ける
起き上がる・立ち上がるときはゆっくりと。急な動きはめまいを悪化させる原因になります。 -
体を冷やさないようにする
首元や足元を温めて血流を促進しましょう。特に冷えやすい方は靴下やブランケットの活用を。
無理に動こうとせず、まずは「落ち着くこと」が何より大切です。
そのめまい、危険かも?受診のタイミングとチェックポイント
めまいの多くは一時的なものですが、次のような症状を伴う場合は、早めの医療機関の受診が必要です。
-
数日経っても改善しない
-
繰り返し何度も起こる
-
頭痛や吐き気、手足のしびれを伴う
-
意識がもうろうとする、言葉がうまく出ない
-
歩行が困難になる、転倒しそうになる
これらは「脳の病気」や「内耳の重大な疾患」のサインである可能性もあります。
特に高齢の方や持病がある方は要注意です。
また、「ただの疲れかな」と自己判断して放置すると、症状が慢性化することも。
違和感があるときは、かかりつけ医や耳鼻科、必要に応じて脳神経外科を受診しましょう。
東洋医学で考える「めまい」とは?鍼灸での対処法
東洋医学では、「めまい」は身体の気(エネルギー)と血(けつ)の流れが乱れた状態と考えます。
特に次の3つの状態が原因としてよく挙げられます。
-
肝の高ぶり(肝陽上亢):ストレスや怒りによって気が上にのぼり、頭がふらつく。
-
気血の不足(気血両虚):体力の低下や食生活の乱れでエネルギーが不足している。
-
痰湿の停滞(痰湿中阻):水分代謝が悪く、体内に不要なものが溜まっている状態。
鍼灸では、これらの原因に応じて「ツボ」に刺激を与えることで、気血の巡りを整え、自律神経や内耳の機能を改善するアプローチを行います。
よく使われるツボには、「風池(ふうち)」「百会(ひゃくえ)」「内関(ないかん)」などがあり、症状に応じて選択されます。
薬を使わずに体質改善を目指したい方には、鍼灸は非常に有効な選択肢の一つです。
めまいを繰り返さないために!日常でできる予防とセルフケア
めまいの再発を防ぐには、日常生活でのセルフケアがとても重要です。以下のポイントを意識して生活を整えていきましょう。
-
睡眠をしっかりとる
睡眠不足は自律神経を乱す最大の要因です。毎日6~7時間以上の質の良い睡眠を心がけましょう。 -
ストレスを溜めすぎない
ストレッチや散歩、趣味の時間を取り入れることで、心身の緊張をやわらげます。 -
バランスの良い食事
ビタミンB群や鉄分、マグネシウムなど、神経の働きを支える栄養素をしっかり摂取しましょう。 -
水分をこまめに補給する
体内の水分バランスが乱れるとめまいのリスクが高まります。特に朝起きた直後は意識して水を飲みましょう。 -
姿勢を意識する
猫背やスマホ首は、首肩の血流を悪化させ、めまいの引き金になります。背筋を伸ばすだけでも予防になります。
また、定期的に鍼灸や整体で体のメンテナンスを行うことで、体質を整え、めまいの出にくい状態を維持することができます。
【まとめ】めまいを正しく知って、安心できる毎日を
めまいは誰にでも起こりうる身近な症状ですが、その原因や対処法を知っておくことで、不安を大きく減らすことができます。
突然のめまいには、落ち着いて対処することが第一。生活習慣を見直し、鍼灸などの東洋医学的なケアを取り入れることで、体質から改善を目指すことも可能です。
「ただの疲れ」と軽く見ず、必要な場合は医療機関に相談することも忘れずに。めまいのない、快適な毎日を手に入れるために、今日からできることを始めていきましょう。
当院では
当院では、めまいに対し、鍼灸治療と、徒手療法を併用して行います。
めまいに関わるものとして、脳圧と呼ばれるものがあります。
脳圧とは、その名の通り、脳にかかる圧力のことですが、頭を強く打って、頭の骨の中で出血が起こったりすると脳圧が上がりますが、この状態は病的なものをいいます。
病的じゃないもので脳圧が上がっているものもあり、脳脊髄液と呼ばれる脳、脊髄の周りを巡る液体がうまく吸収されない、またはたくさん出すぎている状態であれば、病的な範囲ではない状態で脳圧が上がっているものになります。
この脳脊髄液の流れを改善していくことが大切になります。
鍼灸でツボや筋肉に対してアプローチし、頭や背骨などへのアプローチで脳圧を下げることもできます。
慢性的な脳圧の上昇は様々な不調を引き起こしますが、めまいもその一つになっています。
そこに対し、アプローチを行うことで、めまいの患者様が、めまいが減ってきたと喜んでいただいております。
めまいにお悩みの際には、一度病院へ行ってから当院へご相談くださいね!
キトキト鍼灸接骨院のアクセスマップ
大阪市東成区大今里2-11-27 岡本ビル1階
地下鉄千日前線今里駅、新深江駅徒歩約10分
この記事の監修者

「身体を変える。未来を変える。」
キトキト鍼灸接骨院 院長 中土 育弘(なかつち やすひろ)
経歴
- 東洋医療専門学校 鍼灸師学科卒業
- 平成医療学園専門学校 柔道整復師学科卒業
- 明治東洋医学院専門学校 教員養成学科卒業
- 東洋医療専門学校 専任教員
- 2023年10月 キトキト鍼灸接骨院 開業