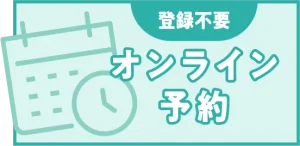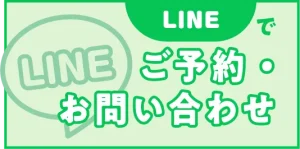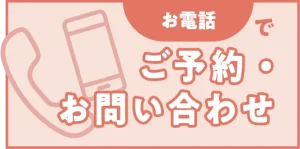肩こりはなぜ起こるのか?対策と治療方法について
歪み×コリ×内臓から身体を根本から整えるキトキト鍼灸接骨院です!
肩こりで悩まれている方は多いのではないでしょうか?
- デスクワークや勉強で肩こりがひどい
- 肩こりがひどくなると頭痛がする
- 慢性的に方が凝りすぎて石みたいになっている
など言われる方が多いですね。

今回はそんな肩こりについてメカニズムと原因そして、当院での施術について解説していきます。
肩こりについて
肩こりは様々な原因により起こります。
挙げだすときりがないですが、東洋医学では
「肩こりは万病の元」
という表現もありました。
肩こりは血流循環が悪くなった結果筋肉が異常収縮している状態です。
これを放置しておくと、いろいろな病気や病院では診断がつかない症状の原因になると言われています。
肩こりは、姿勢や腕の使い過ぎ、首の使い過ぎ、内臓の負担などが原因で起こります。
肩こりがひどい方は寝違えにもなりやすく、背骨の柔軟性が悪くなっている場合もあります。
さらにひどくなってくると、呼吸が浅くなり、自律神経が乱れてきます。
自律神経の乱れ
↓
睡眠の質の低下
↓
疲れが取れにくい
↓
筋肉が硬くなる
↓
血流循環が悪化
↓
肩こり
↓
自律神経の乱れ
といった悪循環をどこかで止めないと、肩こりは続き、自律神経に異常が出てきます。
そうならないためにも、日ごろの身体のケアをしっかりと行っていただくことが大切です。
肩こりになりやすい姿勢
なかなか良い姿勢って難しいですよね。

放っておくと、猫背、巻肩、ストレートネックの状態になります。
スマホやパソコンなどを使いすぎて頭が前に出てしまっている方多くいらっしゃいますので、スマホやパソコンを使う姿勢こそ意識していただきたいと思います。
頭の重さは約5キロ、ボーリングの玉ぐらいの重さがあります。
それを頑張って支えているのが、首から肩にかけての筋肉です。
頭が前にある状態は、まさにボーリングの玉を少し前にして持っている状態です。
ずっとその状態だと、腕プルプルしませんか?
首や肩がどれだけ頑張っているのか分かりますか?
その姿勢をずっとしてると、首や肩は悲鳴を上げるにきまってますよね。
そんな悲鳴を放置していると、石のような肩こりが出てきます。
なので、首や肩の悲鳴に耳を傾けてあげてください。
血流循環が悪いと、自律神経にも影響が出て、疲れが取れなくなったり、頭痛が出たりしてきます。
日々の姿勢を気を付けるだけでも肩こりはどんどん良くなっていきますので、姿勢のケアをしていきましょう。
猫背で巻肩、ストレートネックの状態で、肩を触ってみてください。
肩の筋肉が硬くなってますよね!
これを姿勢を正して、胸張って巻肩を戻し、頭の位置を肩の上に持ってくると、肩の筋肉が緩んでませんか?
その状態をキープすることが大切です。
日々の負担を減らして、肩こりの原因を取り除いていけば、あなたの肩こり、首こり、頭痛は改善していきますので、ぜひ試してみてください。
日々の生活を変えるお手伝いをさせていただきますので、一度ご相談くださいね!
肩こりの筋肉
肩こりと言えば、「僧帽筋」です!僧帽筋は首と肩甲骨、背骨をつなぐ大切な筋肉です。

姿勢が悪くなり、背中が丸くなってくると、この筋肉は引っ張られて使えなくなってきます。
使えなくなった筋肉は、弱くなり、硬くなり、血流循環が悪くなるため肩こりを引き起こします。
使えなくなった筋肉があれば、使いすぎてしまう筋肉があります。
それが胸鎖乳突筋です。耳の少し前の乳様突起と呼ばれる出っ張りから、鎖骨と胸骨につく筋肉ですが、この筋肉は、首を動かすときにすごく使う大切な筋肉です。

猫背、ストレートネックの状態になると、この筋肉は使いすぎて凝り固まってしまいます。
緩め方はさするだけでもOK!
つまんで下へ揺らすのも良いですね!
これを継続することで、肩こりはどんどん変わっていきます。
また、胸鎖乳突筋以外に、重要な筋肉として肩甲挙筋があります。
この筋肉は肩甲骨から首につく筋肉ですが、頭の重みを支えている僧帽筋がうまく働かなくなった時に、この筋肉が首を支えてくれています。肩甲骨の内側の上の方が辛いという場合は、この肩甲挙筋が硬くなりすぎて凝り固まっている状態です。

しかし、根本的なところはこの場合、姿勢になりますので、姿勢を改善していくことが必要になります。
正しく身体を使えるようになることで、僧帽筋、胸鎖乳突筋、肩甲挙筋はうまく働いてくれる状態になります。
この状態を目指して、ストレッチやトレーニング、日々の姿勢を意識していくことで、身体はどんどん変わります。
ただ、セルフケアにも限界があります。
悪くなるものを止めるのはできますが、良い状態になっていくには、かなり頑張らないと難しいです。
また、背骨の柔軟性は、様々な原因により起こるため、その原因を除去していくことで、早く良くなっていきます。
肩こりと内臓の関係

内臓と肩こりって関係ないように思えますが、実はとても関係が深いんです。
内臓なので、食べ物や飲み物とも深く関わりますが
例えば
- お酒を飲み過ぎた
- 毎日お酒を飲んでいる
こういった場合に、負担がかかる臓器ってわかりますか?
「肝臓」ですよね!
では
- 毎日お腹いっぱいたくさん食べてる
- 食べ物をほとんど噛まずに食べている
こうなった時に負担がかかるのは・・・
「胃」ですよね。
病気までいってなくても、こういったことで負担がかかるということはなんとなくわかるんじゃないでしょうか?
食事の内容にもよりますが、脂っこいものを食べていれば、肝臓や胆のうに負担がかかりますし、タンパク質を過剰に摂取していれば肝臓や腎臓に負担がかかります。
内臓に負担がかかりすぎると、「内臓体壁反射」というものが起こり、内臓に応じて硬くなる筋肉が出てきます。
その結果、慢性的な肩こり、首こりなどにもつながります。
こういったことは一例ではありますが、食事の内容や、よく噛む習慣を身につけけるだけでも肩こりは改善することがあります。
できることからやると、お金がかからずに済みそうですね!
噛むだけならタダですよ!笑
しかし、内臓の負担は、自分ではあまり気づけないものです。
身体にどんな反応が出ているのかを自分で判断はなかなかできるものではありませんので、内臓へのアプローチを行っているような専門家に相談いただくことをおすすめします。
肩こりと腕の関係

今回は、肩こりと腕の関係性について解説していきます。仕事でデスクワークの方、パソコンを触る機会が多いと思います。
そういった場合に、気づけば腕はパンパンになっていて、肩こりもつらい。という方が多くいらっしゃいます。
腕の疲れが首や肩のこりにつながるのはなぜなのでしょうか?
パソコンの仕事では、指を良く使います。
指の神経は首から出ていて、肩や胸を通って指先へ行きます。
腕の筋肉の神経も同様ですが、指を動かす筋肉や、腕の筋肉が硬くなることで、神経が引っ張られてしまいます。
神経が引っ張られると、神経の近くにある血管は収縮し血流循環が悪くなっていきます。
神経や血管の状態が悪くなると、首や肩の部分の関節に影響が出て、動きが悪くなってしまいます。
そうなってくると、筋肉はより関節を動かすときに負担を強いられるわけですね。
結果、肩こりや首こりなどの症状が出てきます。
そして、腕を使う際には、手は前に出している状態が多いですよね。
気づけば、肩は前に出て、巻肩の状態になります。
姿勢が悪くなれば、頭は前に出て、背中が丸くなっている状態で、姿勢の悪さからも、首肩の筋肉が引っ張られて負担がかかります。
この状態を長時間続けられていると、結果的に首肩周りの筋肉はガチガチに固まり、肩こりが完成してしまいます。
こうならないためにも、日々の姿勢の意識や、指、腕のストレッチを行って肩こりになりにくい状態をつくっていくことが大切です。
当院では
当院では、首こり、肩こりの方に対し、背骨や骨盤、内臓、筋肉、神経などからアプローチすることで、お身体を根本から整えていきます。
骨格・骨盤矯正

骨盤や全身の関節にアプローチし、身体の重心バランスを整えます。
足首や股関節、背骨、手首などにもアプローチして、本来の関節の動きを取り戻します。
身体の重心バランスが整えば、姿勢も改善されて、肩こりや首こりが出にくい状態になります。
頭の位置や背骨のS字のカーブを整えることで、身体はどんどん変わっていきます。
内臓調整

内臓の膜へアプローチして、内臓の本来の動きを取り戻します。
内臓の負担は背骨の柔軟性の低下により、肩こり、首こりの原因になります。
そうならないために、内臓へのアプローチはかかせません。
あなたのつらい肩コリや首こりの原因は意外と内臓にあるかもしれませんよ。
自律神経調整

自律神経の乱れは、睡眠の質の低下や首肩のこりの原因になります。
自律神経に影響が出るような、首や胸、頭などにアプローチすることで、自律神経の本来の働きを取り戻し、身体がしっかりと回復できる状態に戻します。
頭のアプローチで首の筋肉が柔らかくなることも多いので、リピーター続出です!
また、日ごろの負担がかかりやすい状態になっていれば、その対策としてのセルフケアの指導もさせていただいておりますので、ぜひ一度当院にご相談ください。
キトキト鍼灸接骨院のアクセスマップ
大阪市東成区大今里2-11-27 岡本ビル1階
地下鉄千日前線今里駅、新深江駅最寄り
この記事の監修者

「身体を変える。未来を変える。」
キトキト鍼灸接骨院 院長 中土 育弘(なかつち やすひろ)
経歴
- 東洋医療専門学校 鍼灸師学科卒業
- 平成医療学園専門学校 柔道整復師学科卒業
- 明治東洋医学院専門学校 教員養成学科卒業
- 東洋医療専門学校 専任教員
- 2023年10月 キトキト鍼灸接骨院 開業